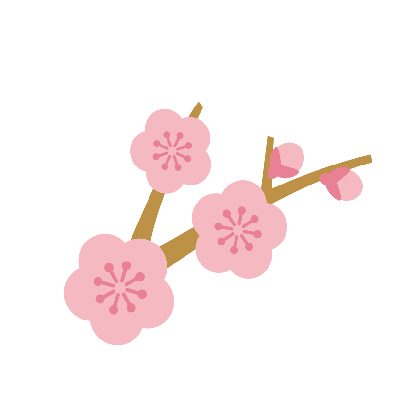
60歳まで小倉で暮らして今は博多に住んでいる私。先日ご近所さんに「山際さんエレベーターの中で、よくご主人と喧嘩していらっしゃいますね、ホホ・・」と。えっ!エレベーター内は公共の場所、いくら何でもそこで喧嘩した記憶はありません。あーそうだ私たち夫婦の小倉弁が博多の人には言い争いに聞こえているのかもしれません。語尾に「ち」とか「ちゃ」をつける小倉弁は大好きなのですが。
今から10年ほど前も冷や汗をかいたことがあります。東京のホテルで知り合いの女性と待ち合わせをしていましたが、居場所がわからず何度も携帯に連絡を入れました。やっとホテルのカフェにいるのを見つけ「ジャンジャン電話をしてごめんなさいね」と駆け寄りました。すると、知人の連れらしい女性から「じゃんじゃんってどんな意味ですの」と突然の質問。うっかりしていました。ここは高級ホテルなのです。私、一瞬たじろぎましたが気を取り直して「ジャンは一度電話すること。二度かけましたからジャンジャンと申しましたの。覚えておかれると便利だと存じますが」と返しました。人の言葉尻を捉えてきついことをいうニセ貴婦人も存在するので皆さんもご注意くださいね。
ある時はテレビのレポーターさんが泣いているので、どうしたのかと聞くと、年上のゲストに試食品を「食べて下さい」と言ったのをデレクターから「お召し上がりくださいとなぜ言えないのか」ときつく叱られたそうなのです。昔はテレビ局も言葉遣いに厳しかったのです。
皆さんはどうでしょう。「食え」「食べなさい」「お召し上がりください」あるいは「よく来たね」「よくいらっしゃいました」「よくお越しいただきました」など使い分けていますか。普段着の言葉は親しさや親密さを感じさせますが、改まった言葉は尊敬の気持ちを伝えてくれます。
学校の先生にも普段の言葉で話しかける時代に何をと思われるかもしれませんが、子どもさんたちは近い将来、社会に出ます。上司やお客様とのコミニュケーションで普段着の言葉は使えません。そこから「丁寧語」「謙譲語」「尊敬語」などを学び始めるのはどんなにに大変なことか。言葉遣いで社会への第一歩がつまずいてしまうのはもったいないとは思いませんか。私が知人、友人、親戚、職場仲間、ご近所さんなど他者と食卓を囲むのをすすめる理由はそこにあるのです。
「やば」「旨い」「美味しいです」「良いお味です」「美味しゅうございます」いろんな言葉が交わされる食卓こそ学びの場なのです。